ニラと言えばレバニラ炒めやもつ鍋といったイメージでしょうか。
メインとしてたくさん食べる野菜ではないものの、少しの量にも栄養がギュッと凝縮されていること、ご存じですか?
これからお伝えする内容を読むと、
- ニラに多い栄養は?
- レバニラを1皿食べると1日分の栄養の何%が摂れる?
- どんな効果がある?
- どんな人こそ食べるといいの?
といったことが手に取るようにわかります。ニラの栄養を上手に活かして元気な毎日を過ごしましょう。
レバニラ1皿分の栄養価
ニラに多い栄養は、ビタミンA、K、E、C、葉酸、カリウム、水溶性食物繊維など。
一度にたくさん食べる野菜ではないものの、私たちに不足しがちなビタミンA、C、水溶性食物繊維などの栄養が豊富に含まれています。
ニラの効果としては、動脈硬化の予防、心筋梗塞や脳梗塞の予防、感染症から守る、血圧を下げる、貧血の改善、美肌、アンチエイジングなどが期待できます。
では、
どの栄養がどのくらい多くて、
その栄養はどんなはたらきなのか、
ご存じですか?
ニラは一度に100gも食べることはまずありません。ここでは、レバニラ炒めなど一度に食べる量を1/4束(24g)として、
- レバニラ1皿分のニラを食べると、
1日分の栄養の何%が摂れる? - ニラに多い栄養は何?
- どんな効果が期待できる?
というかたちでお伝えします。
一度に食べる量
=レバニラ1皿分のニラ(1/4束:24g)
ニラは1束は株元を除くと95g。この1/4を1食分として24g。生のニラの栄養価ではなく、レバニラ炒めなど「油で炒めたニラに含まれる栄養価」を紹介します。

ニラに多いビタミン
まずはビタミン。
レバニラ1皿分のニラ(1/4束:24g)を食べると、女性の1日分のビタミンの何%が摂れるのか、グラフにしてみました。
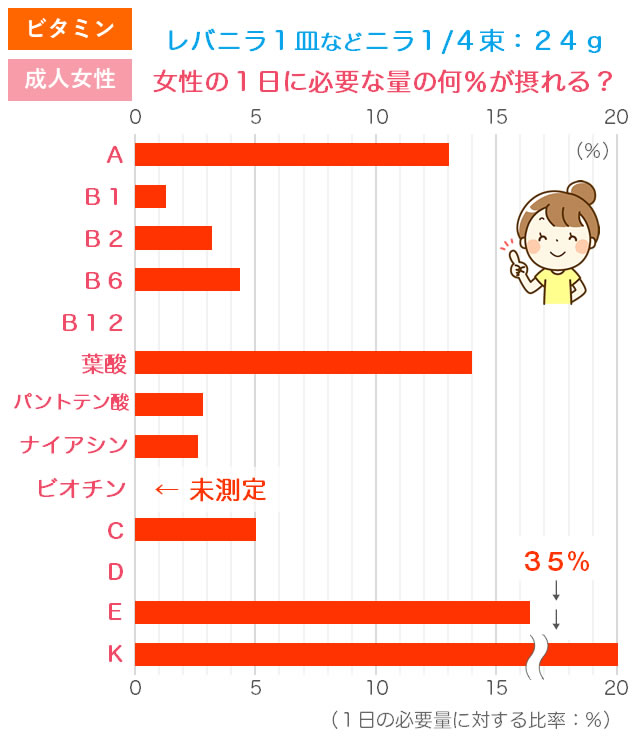
※参考サイト:
文部科学省「食品成分データベース」
ニラに多く含まれているビタミンは次の4つ。女性にとって1日に必要な量の何%が摂れるのかというと……
| ビタミンK | 35% |
| ビタミンE | 16% |
| 葉酸 | 14% |
| ビタミンA | 13% |
わずか24gのニラの中にはビタミンKがたっぷり。血管の掃除役であるビタミンE、貧血を防ぐ葉酸、免疫力を高めるビタミンAも多く含まれています。
ではニラに多いビタミンの効果をお伝えする前に、ニラにはどんなミネラルが多いのかをお伝えします。
ニラに多いミネラル
ニラ1/4束(レバニラ炒め1皿分)で、女性の1日分のミネラルの何%が摂れるでしょうか?
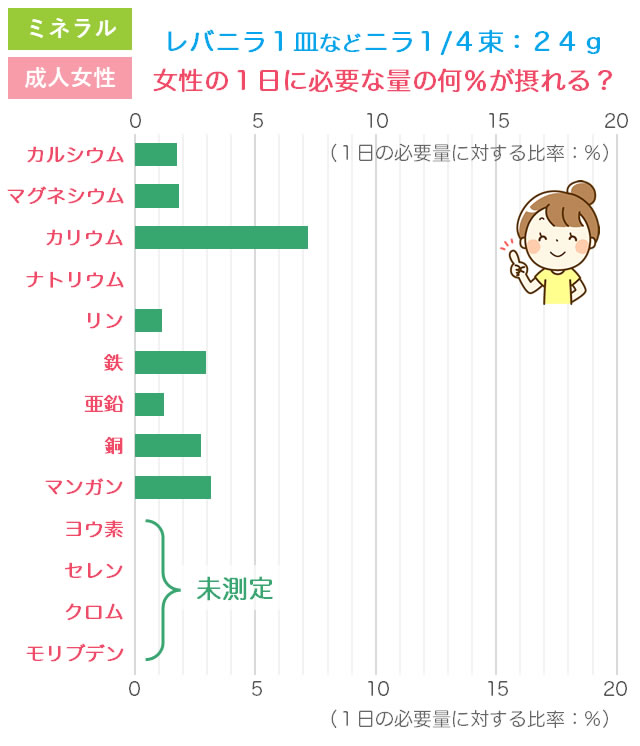
ビタミンと比べるとミネラルは少なめ。その中でニラに多いミネラルはカリウムのみ。
| カリウム | 7% |
次いでマンガン、鉄、銅、などの順に続きますが、どれも3%以下と低めです。
では、ニラの食物繊維をお伝えしてから、ニラの7つの効果効能を紹介します。
ニラに多い食物繊維
ニラ1/4束で1日分の食物繊維の何%が摂れるでしょうか?
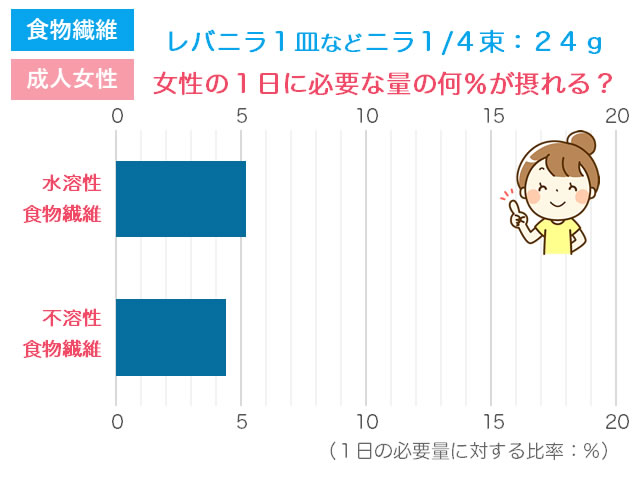
| 水溶性食物繊維 | 5% |
| 不溶性食物繊維 | 4% |
ニラに含まれる食物繊維はどちらも5%前後。わずか24gのニラの栄養価ということもあって少なめです。
では、
ニラに多い栄養には
どんな効果があるのでしょうか?
私たちはその栄養が
ちゃんと摂れているのでしょうか?
ニラに多い栄養とその効果

ニラ1/4束24g(レバニラ炒め1皿分)に含まれている栄養の中で、女性の1日分の栄養に対して多い順に、
| ビタミンK | 35% |
| ビタミンE | 16% |
| 葉酸 | 14% |
| ビタミンA | 13% |
| カリウム | 7% |
ではこの5つの栄養は……
- 私たちはどのくらい摂れている?
- ニラ1/4束でどのくらい補える?
- どんなはたらきがある?
についてお伝えします。
ビタミンK
ニラにもっとも多い栄養はビタミンK。強い骨をつくる、出血をとめるはたらきがあります。
ニラのビタミンKの量は?
1日に必要なビタミンKは
女性も男性も150μg。
ニラ1/4束には53μg。
1日に必要な量の35%です。
さて私たちは普段からビタミンKをどのくらい摂れていて、ニラを1/4束食べるとどう増えるのかというと……
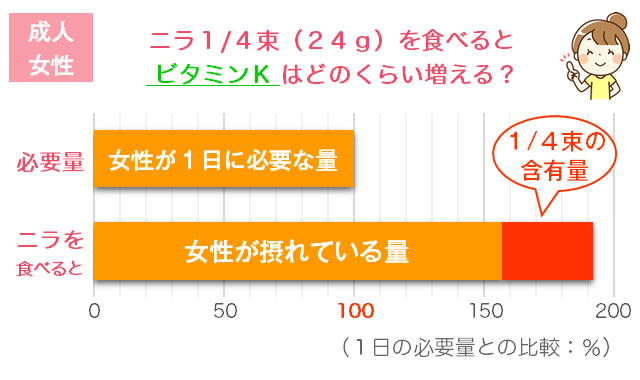
女性が摂れている量は、157%
ニラ1/4束に、35%
合計で、192%
男性が摂れている量は、164%
ニラ1/4束に、35%
合計で、199%
ビタミンKはいろんな食べ物に広く含まれている栄養。普段から十分摂れています。
ただ、食生活がかたよっていたり、抗生物質を長期間飲み続けている人は不足しがちな栄養です。
※参考サイト:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」、国立健康・栄養研究所「主な健康指標の経年変化:栄養摂取状況調査」
ビタミンKの効果は?
おもなはたらきは次の2つ。
- 丈夫な骨をつくる
- 切り傷など出血した血を固めて止血する
なお、食べ物に含まれるビタミンKは3種類に分かれますが、骨粗しょう症対策に高いはたらきをするビタミンKが豊富な食べ物は納豆。
| 1日に必要な量 | 150μg |
| ひきわり納豆1パック | 372μg |
| 粒納豆1パック | 240μg |
| ニラ1食分24g | 53μg |
骨粗しょう症の対策には納豆を取り入れましょう。
【関連記事】ひきわり納豆に多い栄養は?1パックの栄養価と8つの効果
ビタミンE
2番目の栄養はビタミンE。流れを良くするはたらきと抗酸化作用が高く、血管を若々しくしてくれる栄養です。
ニラのビタミンEは?
1日に必要なビタミンEは
女性が6mg、男性が7mg。
ニラ1/4束に1mg。
では普段からどのくらい摂れていて、ニラでどう増えるかというと……
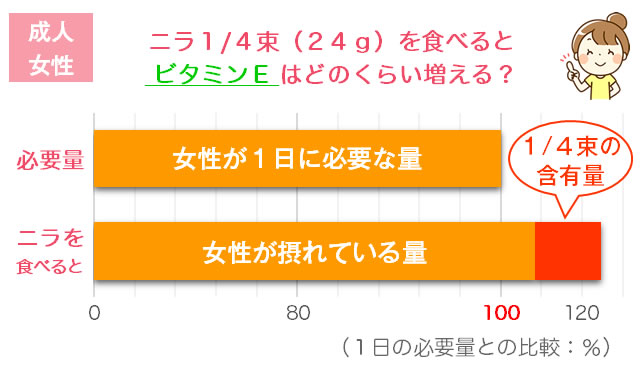
女性が摂れている量は、108%
ニラに、16%
合計で、124%
男性が摂れている量は、100%
ニラに、14%
合計で、114%
※参考サイト:厚生労働省 e-ヘルスネット「LDLコレステロール」、国立健康・栄養研究所「ビタミンE解説」
ビタミンEの効果は?
おもなはたらきは次の7つ。
- 流れをサラサラにして動脈硬化を防ぐ
- 悪玉コレステロールをおさえて、心筋梗塞や脳梗塞を防ぐ
- 心疾患や貧血を予防する
- 血行を良くしてコリや冷えを防ぐ
- 肌や髪を美しく
- 記憶力を高める
- 更年期障害の症状をやわらげる
ビタミンEは血管の掃除役。抗酸化力とサラサラにするはたらきで、血圧、中性脂肪、コレステロールといった生活習慣病を防いでくれます。
葉酸
ニラに3番目に豊富な栄養は葉酸。貧血を防いだり胎児の正常な発育を守るはたらきがあります。
ニラの葉酸は?
1日に必要な葉酸は
女性も男性も240μg。
ニラ1/4束には34μg。
ニラを食べると……
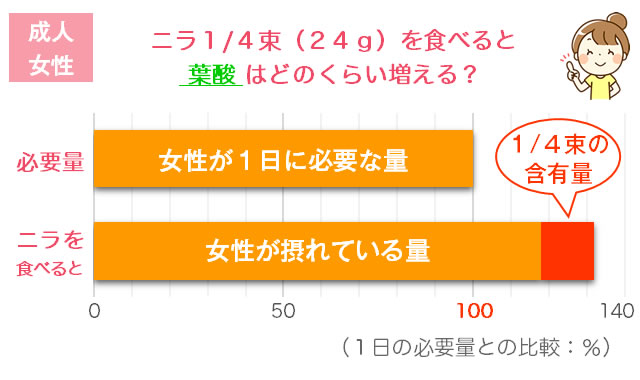
女性が摂れている葉酸は、118%
ニラに、14%
合計で、132%
男性が摂れている葉酸は、123%
ニラに、14%
合計で、137%
※参考サイト:国立健康・栄養研究所「葉酸解説」
葉酸の効果は?
おもなはたらきは次の4つ。
- 妊娠中のお腹の赤ちゃんを正常に成長させる
- 血液(赤血球)を作って貧血を防ぐ
- 細胞をつくるサポート
- 肌や粘膜を守って整える
妊活中の方、妊婦さん、授乳中のママは葉酸を多めに摂ることが大切。枝豆、ほうれん草、ブロッコリーなど多く含まれる食べ物はこちらをご覧ください↓
ビタミンA
4番目の栄養はビタミンA。粘膜を健康にし、免疫を高め、目の健康を守るはたらきがあります。
ニラのビタミンAは?
1日に必要な量は、
女性が700μgRAE、男性が900μgRAE。
ニラ1/4束に91μgRAE。
ニラを食べると……
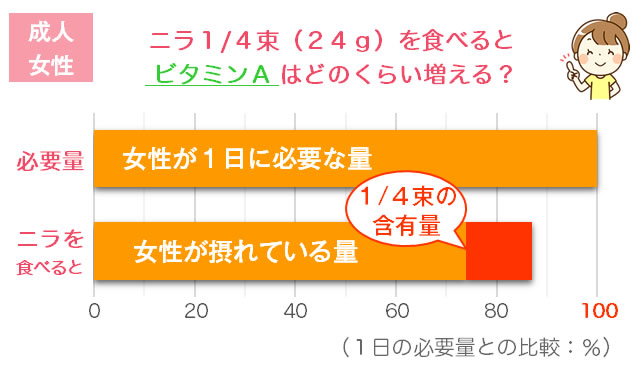
女性が摂れている量は、74%
ニラに、13%
合計で、87%
男性が摂れている量は、61%
ニラに、10%
合計で、71%
ビタミンAは私たちにかなり不足している栄養。ニラにもしっかり含まれていますがまだ足りません。
にんじん、春菊、かぼちゃなど、ビタミンAの豊富な食べ物をこちら↓
ちなみに、レバニラならレバーにビタミンAがぎっしり。豚レバー(約100g)に1日分の20倍ものビタミンAが含まれています。
ビタミンAの効果は?
おもなはたらきは次の5つ。
- 風邪などの感染症から守る
- さまざまな病気や老化の予防
- 美肌・美髪
- 夜盲症を防ぐ
- 子供の成長を促進
カリウム
ニラに5番目に多く含まれるカリウム。血圧ケアだけでなく、体をスムーズに動かしたり心臓のはらたきを守るはたらきもあります。
ニラのカリウムは?
1日に必要なカリウムは
女性が2000mg、男性が2500mg。
ニラ1/4束に144mg。
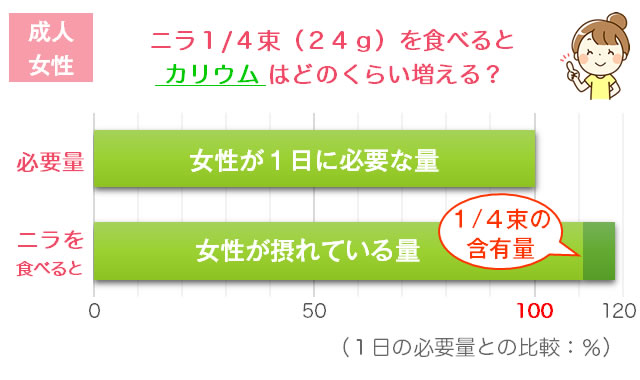
女性が摂れている量は、111%
ニラに、7%
合計で、118%
男性が摂れている量は、96%
ニラに、6%
合計で、102%
※参考サイト:厚生労働省 e-ヘルスネット「カリウム」
カリウムの効果は?
おもなはたらきは次の4つ。
- 余分なナトリウムの排出を促進する
- 血圧を下げる
- 心臓の正常にはたらかせる
- 筋肉をスムーズに動かす
- むくみを解消する
余分な塩分を排出して高血圧を予防するカリウム。塩分の摂りすぎが気になる方は意識して摂りましょう。
*-*-*-*-*
ニラに多く含まれる栄養とそのはたらきをお伝えしました。最後にこれらをまとめて、
ニラを食べると
どんな効果が得られる?
どんな人こそ食べるといいの?
についてお伝えします。
ニラの7つの効果効能
ニラは少ない量でもビタミン類を中心にいろんな栄養が豊富。
これらの栄養のはたらきから、ニラに期待される効果をまとめてみました。
- 流れをサラサラにして動脈硬化を防ぐ
ビタミンEの強い抗酸化力がコレステロールの酸化を防いで、血管をしなやかで健康に状態に維持する - 心筋梗塞や脳梗塞を予防する
ビタミンEが悪玉コレステロールをおさえて流れを良くする - 感染症から守る
ビタミンAが粘膜を正常に保ってウイルスをブロックして免疫機能を高める - 血圧を下げる
カリウムが余分な塩分(ナトリウム)の排出を促進する - 貧血を予防する
葉酸がビタミンB12と一緒になって血液(赤血球)を作り、ビタミンEが流れをサラサラにして全身に酸素を届ける - 美しい肌と髪をつくる
ビタミンA、E、葉酸が肌の新陳代謝を高めて肌にハリとうるおいを与え、美しく黒い髪をつくる - 若々しく元気な体に
ビタミンAとEの高い抗酸化作用で老化や病気の原因となる活性酸素を除去する
ということで、ニラをぜひ食べてもらいたい人は……
こんな人こそニラを食べて!
ニラをぜひ食べてほしい人はこちら!
- 血圧が気になる
- お腹まわりが気になる
- 脂っこいものや濃い味つけが好き
- 運動不足
- 風邪をひきやすい
- 貧血ぎみ
- 肩こり、むくみ、冷え性
生活習慣病を予防したい。感染症にかかりたくない。コリや冷えなど巡りが悪い。といった方にぜひ食べてもらいたいのがニラなのですね。
ニラに多い栄養:まとめ
ニラに多い栄養や健康効果についてお伝えしました。
ニラに多い栄養:1日に必要な量に対して多い順番に、ビタミンK、ビタミンE、葉酸、ビタミンA、カリウム、水溶性食物繊維、ビタミンCなど
ニラの効果:動脈硬化の予防、心筋梗塞や脳梗塞の予防、感染症から守る、血圧を下げる、貧血の改善、美肌、アンチエイジング
どんな人に食べてほしい?:血圧が気になる、お腹まわりが気になる、味の濃いものが好き、運動不足、風邪をひきやすい、貧血ぎみ、肩こり、むくみ、冷え性
ニラ独特の辛味成分には高い殺菌効果や抗酸化作用があって、感染症から守り、疲労回復を高めるはたらきが期待されています。
忙しい毎日の疲れやストレスから守るためにも、ふだんの食生活にぜひニラを取り入れてみてはいかがでしょうか。





